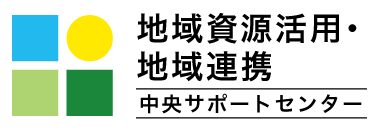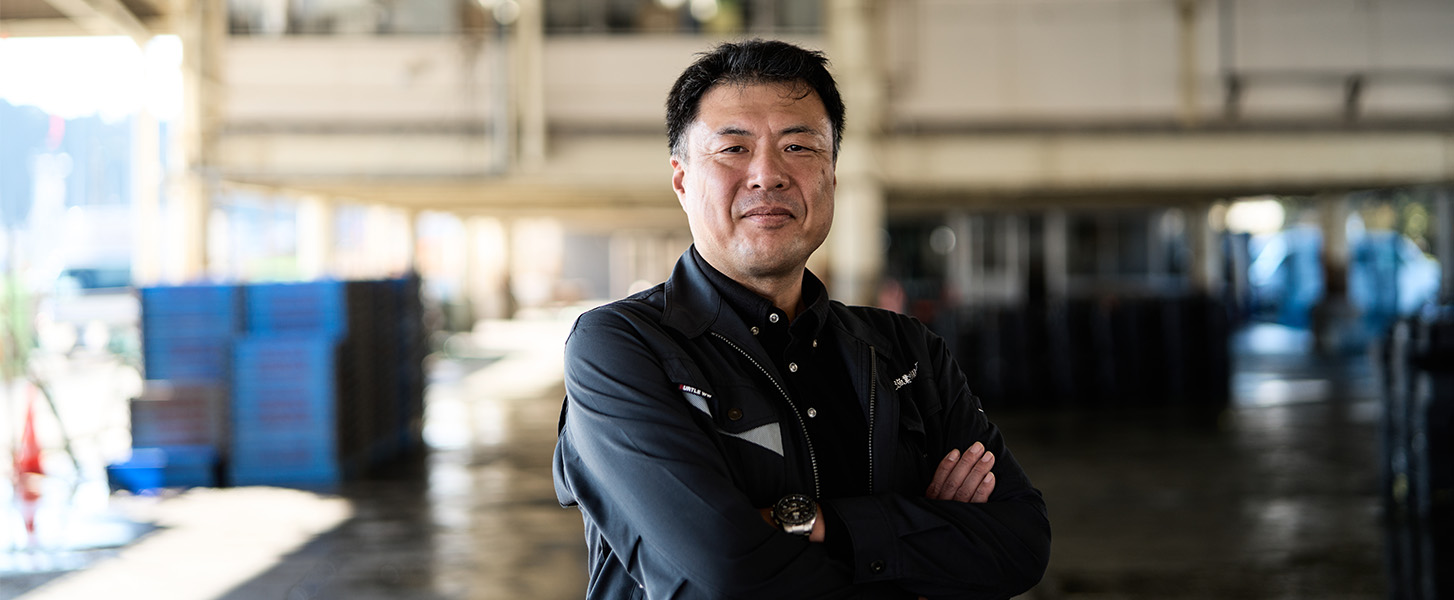
新発想で水揚げに左右されない経営基盤を/伊豆漁業協同組合参事中川裕介さん
8漁協合併により発足
幕末にペリー艦隊が入港し、日本の開国へのきっかけとなったことで知られる下田港。170年以上の歴史を持つ港です。伊豆漁業協同組合は、2008(平成20)~2009(平成21)年にかけて伊豆半島東部から南部、西部に至る8漁協が合併し発足。旧下田市漁協を本所に、7支部を配置しています。下田では昭和40 年代までアジやサバ、高級魚であるメダイなどが主流でした。メダイと一緒に揚がるキンメダイは当時販路がほとんどない状況でしたが、全国各地の市場への地道な働きかけが実り価値化。高度経済成長の活況下で下田はキンメダイの集積地となり、卸値も上昇を続けて地域ブランドに成長、現在まで全国一の水揚げ量を誇っています。

近年、海水温上昇や海洋資源の変化、漁業者の高齢化等の課題が増える中、伊豆漁協内では水揚げを販売する以外のビジネスを模索する動きが始まりました。初めに手掛けたのは2003 年に開設された「道の駅 開国下田みなと」内に開いた「伊豆漁協ベイステージ直売所」。現在参事を務める中川裕介さんは「しかしこの頃はまだ危機感も薄く、誘われたから出店してみた、という程度。売上もトントンくらいでした」と振り返ります。
市場内にキンメダイをテーマにした食堂開設
BtoC事業に本腰をいれるきっかけを作ったのは、前組合長。市場内に特産のキンメダイを生かした食堂「金目亭」を開設しました。卸売市場内の出店に関する規制を一つ一つクリアし、最初は簡易的に囲いを作る形でスタート。キンメダイのブランド力と「市場の中の食堂」というコンセプトが注目を集め、予想以上の集客と収益を上げました。翌2015年には、拡張・リニューアルで収容人数を増やし順調に運営しています。

「水揚げ以外で稼ごうという意識が生まれたのは、金目亭ができてから」と中川さん。当時の漁協内は保守的な考えが主流で、目新しいことをしようにも反対意見が大半でなかなか前に進みませんでした。しかし当時の組合長は積極的に他の事例を視察し、学び吸収して、計画を提案。「まさに鶴の一声でしたね、反対させないぞっていう。そして実際に儲かったのだから、見事な手腕です」。中川さんは愉快げに振り返ります。なぜネガティブなムードを突破できたのか。「組合長は遊漁船も経営し、民間の開けた思考を多分に持っていた。なおかつ組合員。外部の人が突然アイデアを持ち込んでも反発されるが、組合長自ら携わるという内部からのエネルギーのおかげで全体が動いたと思います」。
機能性表示商品への挑戦と直売所強化
食堂事業の順調なスタートを受けて、BtoCの横展開も始まりました。山梨大学との連携による、キンメダイの筋肉中に含まれる機能性成分の解明と商品化の検討です。すでに大学で一年間データを蓄積して研究を行い、現在は機能性表示の申請を行っている段階。「二枚開きの冷凍・真空パック商品を、機能性表示を付けて売り出すことを目指しています」と中川さん。完成した商品をいかに多く販売するかということより、主な目的はキンメダイの価値と価格の向上です。ホームページも刷新予定で、機能性表示が実現すればイーコマース販売も視野にいれています。

前述した既存の直売所「ベイステージ」は、エグゼクティブプランナーの佐藤さんと連携し販売強化に取り組んでいます。販売経験はないものの意欲と熱量にあふれる店長を抜擢し、エグゼクティブプランナーのアドバイスのもと店舗運営を見直しました。シーズンごとの客層の分析とそれに合わせた仕入れ・商品配置、効果的なPOPの制作と活用、ランキング形式で商品紹介を行うなどのテクニック、SNSを中心とする発信といった多角的な取り組みを実施しました。これらが奏功し、売上は右肩上がりを続けています。
海資源の収益化へ、タブーをなくし挑戦する
エグゼクティブプランナーの佐藤さんの支援のもと、海の資源を収益化する様々な試みも進められています。一つは田子漁港でサービスを開始した釣り場予約アプリ「海釣りgo」。ルールを守らない釣りレジャーは以前から課題でしたが、このアプリの導入によって漁業者は安心でき、釣り人は適切なルールのもとにレジャーを楽しむことができ、漁協にとっては既存資源の収益化につながります。中川さんは「三方良しのいいシステム。田子では非常に好評だと聞いているので、下田でも実施を検討しているところ」と話します。もう一つは安良里支所で漁協所有地にオープンしたグランピング施設。事業者からの提案を受けて連携し、運営は委託しています。今後は下田漁港施設の建て替えが予定されており、隣接する道の駅との連携を含めた地域活性化拠点としての構想を検討中です。

「何もしなくても収益が上がったのは過去の話」と中川さん。漁協は漁業者の生活を守ることを使命に、水揚げに左右されない経営基盤を築く必要があると考えています。エグゼクティブプランナーの支援を通じて海産物の価値向上や、付加価値化による商品開発だけでなく、海の資源を多角的に捉えアイデアを出していくことを学びました。「ジェットスキーの受け入れや宿泊業など、やれそうなことはたくさんある」。柔軟な発想と決断力で金目亭を成功に導いた前組合長から、学ぶことは多かったという中川さん。伊豆漁業協同組合は“タブー” をなくし、従来の常識にとらわれずチャレンジを続けます。