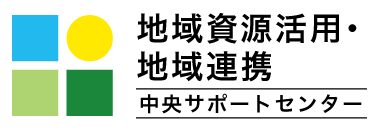卵をコアにした地域循環の実現へ/東海林養鶏場代表東海林肇さん
自社ブランド卵を体当たりで売り込む
秋田県東南部、内陸の盆地にある横手市。一大穀倉地帯として知られ、伝統的なかまくら行事がある豪雪地帯でもあります。東海林養鶏場は1952(昭和27)年に創業。父の後を継ぎ代表を務める東海林肇さんは、卵をめぐるイノベーションで地域の経済循環を起こそうと奮闘しています。
東京で大学・社会人生活を送った東海林さんは、25歳で帰郷し家業に入りました。養鶏の仕事を始めて最初に感じたことは「働いても働いても儲からない」。価格は相場に左右され自分で値決めができず、日々の仕事は多く休みもない。「目の前の仕事に追われるばかりで、課題解決や価値創造にたどり着かない。もっと夢のある前向きな仕事に変えられないか」。東海林さんは考え続け、40代半ばの2006年頃から自社ブランドの構築に着手します。「つなぎ、めぐる、たまご」をコンセプトに、「もらってうれしい卵」「誰かにあげたい卵」を目指してエサや飼育方法を試行錯誤しました。

味に自信を深めた東海林さんは、飲食店や病院などに飛び込み営業を展開し、自社の販売ルートを開拓しはじめます。「秋田県内では、岩手の卵を使う店が案外多いんです。秋田県外産の卵や卸から買っている飲食店をしらみつぶしに回りました。とにかく食べてくれれば違いが分かるはずだ、と思っていました」。こうして直販先を増やし、東海林さんは仕事にやりがいを見出していきます。
味へのこだわりとデザインの両輪
さらなる品質向上を追求しようと、JA全農北日本飼料組合や秋田県総合食品研究所に相談しながら研究を重ね、2012年頃に開発したのが現在の主力商品「至福のたまご 黄身の余韻」です。「何百人もの人に食べてもらいながら改良を重ねた、段違いのおいしさ」と胸を張る自信作。しかしその反面、1個50 円という価格は飲食店では使いづらい卵でした。そこで東海林さんはBtoCに目を向けます。2020年にはデザイン会社と連携してブランドブックやパッケージデザインなどを新たに制作し、味だけでなく「見てワクワクする」広報性をプラス。このときの経験を「商品を手に取ってもらうためにどうデザインするか、という視点が新鮮だった。とても勉強になりました」と振り返ります。

「黄身の余韻」は特に道の駅で好評でした。購買層の中心は観光客と考えていましたが、閑散としたコロナ禍に逆に売り上げがアップ。「地元の固定ファンができていた、と嬉しかったですね」と東海林さん。「徹底的に味にこだわったことで地元に愛される商品になった。やってきたことは間違っていなかった」。一度食べたら他は食べられない“ 悪魔の卵” とも呼ばれ、手土産やギフト用に購入する人も増加。昔から目指していた「もらう喜びから贈る喜びへの連鎖」が、ここで本当に実現したと感じました。
既存の商品ブランドを基盤としたビジネスの横展開
研究と新商品開発が成果を上げたことで探究心に火がつき、卵以外の商品や加工品の開発にも取り組み始めました。パティスリーとの連携によるスイーツやお菓子の開発など引き合いも多く、さらに卵からつくる醤油など、興味の赴くまま意欲的に手を広げました。エグゼクティブプランナーの支援が入ったのはこの頃。さらに商品の幅を広げていこうとしたところ、エグゼクティブプランナーの小野寺さんより「一旦試作をストップしましょう、と言われました」と東海林さん。やりたいことが多いわりに、売上を向上させるための商品化のめどがほとんど立っていなかったのです。今新商品開発に手を出すより、「地に足ついた既存の商品ブランドを活かした戦略を考えたほうがよい。」というプランナーの助言で、もっとも売り上げの伸びが期待できる直売所販売に注力し、POP 作成や販売手法を改善。新規の販路としてふるさと納税や郵便局内での無人販売、企業の福利厚生の一環としての無人販売のルートを開拓し好評を得ました。

その後、念願だった親鶏の食肉化とブランディング、加工品開発にも、プランナーの支援により着手。「こまち美鶏」を商標登録し、キーマカレーやジャーキーなどを商品化しました。卵ギフトやプリンなど、温めていたアイデアも次々と形にしていきました。「プランナーが方向性を示してくれた。開発だけではだめ、販売までこぎつけることが大事だと学びました」。近い時期に、自社施設内に直売所を開設することも決まっています。
鶏糞たい肥で地域の循環を
自社ブランドの構築を始めてから、価格も販路も自分で決め、顧客の声を直接聞きながら改善を重ねている東海林さん。直売所の売上は継続して右肩上がりです。「当初は東京のバイヤーに買ってもらうことに憧れていたけれど、今は地元で価値を理解してもらう重要性が分かってきた」と話します。
今後力を入れるのは、地域の農家から出るもみ殻に自社の鶏糞を合わせた「EMもみ殻たい肥」。手作業で何度も切り返し、発酵を管理した東海林さんのたい肥は非常に品質が高く、特に家庭菜園愛好者に人気です。養鶏場にとって大きな課題である鶏糞処理と、農家のもみ殻処理を同時に解決し、なおかつ地域にメリットを還元できる循環型事業として発展させる未来図を思い描きます。「うちのたい肥はふかふかの良い土ができて作物の根がよく伸びる。おいしい野菜ができれば、生産者は作る喜びだけでなく“ 売る喜び” を感じられる。私自身“ 売る喜び” で人生が変わりましたから、このたい肥で地域の人々に貢献したい」。これこそ、地方だからできる地域経済循環。東海林さんの夢はまだまだ広がります。