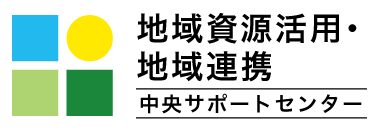全国から届く青果を加工する農産加工OEM のプロフェッショナルに/有限会社エスランドル代表取締役上釡勝さん、専務取締役上釡文子さん
糖度の高いかぼちゃを持って、自ら販路を開拓
鹿児島県南九州市の畑の中にある青とオレンジの壁が目立つ建物は、有限会社エスランドルの3代目の加工場。この特徴的なデザインは、代表取締役であり建築士として店舗設計も行う上釡勝さん。祖父の代から、らっきょうとかぼちゃを育てている兼業農家の家で育った勝さんは、芸術的な面を父から後押しされて東京で店舗デザインの仕事をしていました。その後、父親の病気をきっかけに鹿児島に戻り、最初は建築士として独立します。だんだん建築の需要の減りを感じた2006年頃から文子さんと二人で父の農業を手伝うことにしました。当時、会社を退職し農業に専念していた父親が畑仕事をメインに行い、勝さんは営業を担当していました。それまで農産物はJA などを通して市場に卸していましたが、文子さんが友人にかぼちゃをプレゼントしたときの反響が大きかったことがきっかけで、勝さんは直接小売店に販売する戦略に切り替えました。

まず行なったのが、商標登録。育てていた2品目で「極利かぼちゃ」、「白宝らっきょう」という商標を取得しました。さらにかぼちゃはメロンと同じ糖度15、16度。それならとメロンと同じように木箱に入れ、手間ひまかかる経費等を正しく反映させ市場の2-3倍の値がつくかぼちゃを持って、勝さんはバイヤーにアプローチを行いました。そこから始まったスーパーでの試食販売はいつも売り切れるのに、なかなか他の店からは声がかからず、ついに東京の伊勢丹のバイヤーへのアプローチを始めました。数回断られたのちに、やっと味を認めてもらい、店頭販売が可能となりました。そこでも試食販売を続けて、いまは多くのファンに愛されています。
廃棄の悔しさから始めた農産物加工
伊勢丹から始まり、都市部の百貨店での取扱いが増えて行くなかで、大きな課題がありました。それはどこの百貨店も保管場所が少なく少量でしか送付ができないため、自分たちが大量のかぼちゃを保管する必要があること。そしてある年、暑さのせいで多くのかぼちゃをダメにするという事態に見舞われました。勝さんは「かぼちゃを捨てたことが本当に悔しくて、同じ経験を2 度としないために加工を学びにいきました」と話します。加工は一から学んだため、試行錯誤が続きました。らっきょうの瓶詰めを作り始めた際には、ビンの蓋が錆びつく、味がばらつくなど失敗。そこから味の安定のさせ方などの学びを積み重ねで今があると、2人は言います。また当時は、野菜の加工はペーストやピューレが主流でしたが、それでは冷凍保管が必要となるため、勝さんは乾燥に注目しました。そして同じように生野菜の販売の難しさを味わっている他の農家から一部青果を買い取り、加工をするようになっていきました。

多くの農家から請け負った野菜加工のノウハウを活かしてOEM を開始
乾燥加工は、乾燥することで水分が飛び、実際に使用している量で見積もる金額と実際の出来上がりからイメージする金額の乖離が出てしまうことから、営業にはかなり苦労しましした。ただいくつも訪ねたなかで、都内のスイーツ屋さん1軒に気に入ってもらい、そこから農産加工の会社ということが広まっていき、OEMの話が来るようになりました。その当時は約35品目販売しており、毎日ラインも変えて稼働し、さらに食品の在庫を抱えるというリスクもあったので、一度整理を行いました。そしてここまで多様な品種の対応をしてきたノウハウを活かせるのがまさにOEMでした。他の加工会社はt(トン)単位で受け付けているところを100キロ単位での受付で始めたところ、多くの依頼がくるように。いつしか、エスランドルに持ち込めばなんとかしてくれるという評判が広まっていきました。
プランナーとともに歩むことでやりたいことの実現スピードアップ
エスランドルの経営発展には農山漁村発イノベーションエグゼクティブプランナーが大きく関わっています。支援が開始した当時、コロナが始まり飲食などが止まってしまい、業務用の売上も減少。経営戦略の転換が迫られておりました。そこで、このタイミングで一度立ち止まってプランナーとともに、経営理念・ビジョンの見直しを実施。そして、「私たちは食の可能性を探求し、お客様に感動をお届けします。」という理念を定め、戦略の転換を始めました。
新しい取り組みとして、直接消費者に「商品」と「おもい」を届ける手段がないという課題もあり、支援を受けて通販可能なホームページからスタート。また、新加工場の建設においては、お客様への品質の約束として、プランナーと伴走しながらHACCPの認証も取得。さらに、らっきょうの良さの根拠をしっかり伝えたいという思いから、らっきょうの機能性に注目。地元の大学とらっきょうの機能面に特化した産学連携の共同研究を開始。この共同研究は仮説が立ち、一定の成果の目途が立とうとしています。これらの取り組みに加え、生産から加工・販売までのビジネスモデルを俯瞰して捉え、プランナーとともにDX( デジタルトランスフォーメーション) にも着手。DX戦略書を策定し、公開するなど自社のビジネスシステムも大きく変化させることができました。

勝さんは「自分たちだけでは失敗を重ねながら遠回りをしてきた。それがプランナーと一緒にやっていくことで近道ではないけど、スムーズに進んで来られた。最初の10年間は本当に時間もかかり、そうすると借り入れも増えて大変だったが、プランナーさんがいることでわたし達がやりたいと思っていることの実現スピードが上がった」と話します。文子さんも「上からのアドバイスではなく、同じチームの一員として共に考え取り組んでくれる」と笑顔で話しました。加工のOEMを広げながらも、最近あった嬉しいこととして「地元の子どもたちが収穫した芋を地域の伝統品である飴に加工して、その味を次の世代に引き継いでいきたいと相談がきたこと」をあげてくれた文子さん。「縁あってここに拠点を置いているからこそ、地域の役に立ちたい」と二人は話します。
そして今後も目標は、野菜加工の日本一になること。全国の農家が継続して行くためにも、何かあったときに頼ってもらえる1番になりたいと勝さん。そしてそのために行っているのは、他の得意分野がある加工会社との連携です。相談がきたときに、場合によってはより得意なところをつなぐ。そういう取り組みを少しずつ広げています。また、他の企業ともあわせて加工のプロフェッショナルの養成を目指しています。「加工は青果によってやることが異なり、覚えることも多く大変な仕事。そのプロフェッショナルを育てることが、これからの日本の農業の存続には欠かせないと思う」と勝さんは力強く話してくれました。