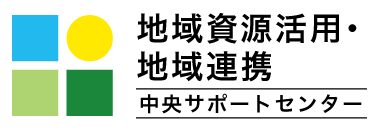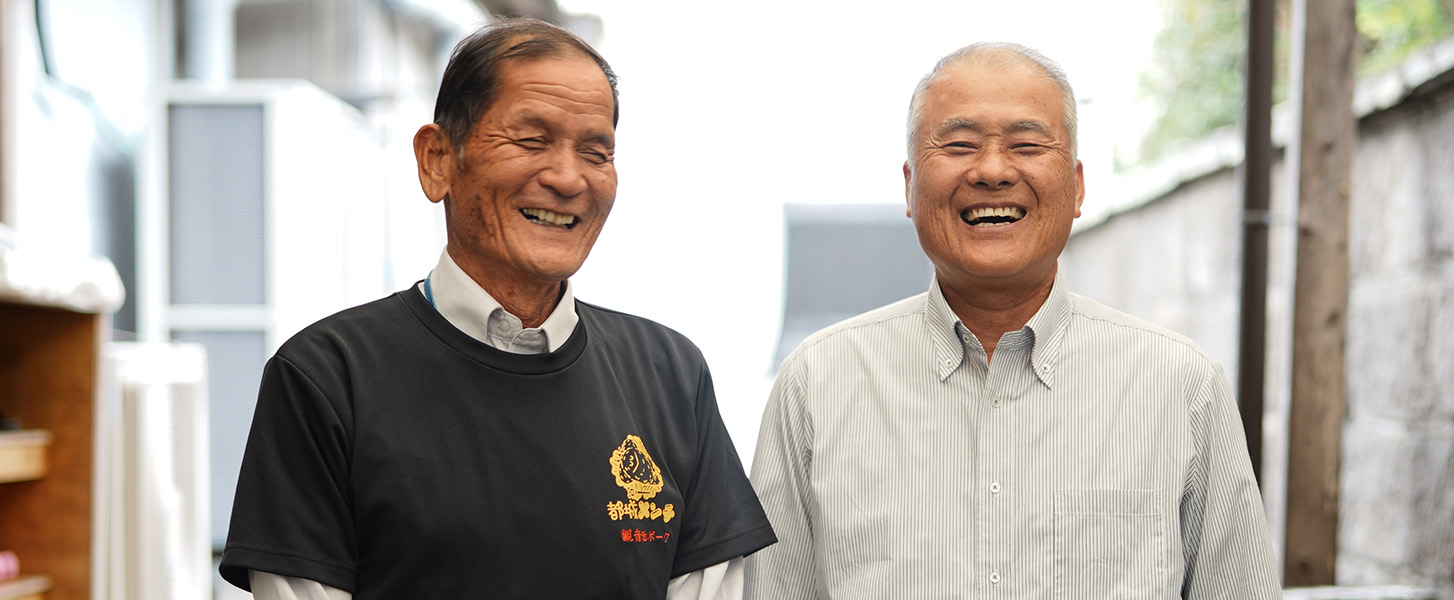
畜産日本一のまち「都城」に新しい景色を創る/有限会社観音池ポーク代表取締役馬場通さん
「子どもたちに安全なものを」がきっかけに
宮崎県の南西端に位置する「都城市」。宮崎市に次ぎ、県内第2の人口を擁する主要都市であり、「ふるさと納税ランキング」では10年連続TOP10入り(2024年現在)を誇る、肉と焼酎のまちです。そんな都城市の盆地の下に湧き出す天然の地下水「霧島裂れっかすい罅水」で養豚業を家族経営から始めた有限会社観音池ポーク。代表取締役の馬場さんはとても穏やかな口調で「40年前、自分たちの子どもたちに安心して安全なものを食べさせたい」と思ったのが銘柄豚を作るきっかけです、と語ってくださいました。

信頼性の高い豚肉をお客様のもとに届けたい
馬場さんは、抗生物質などの残留が懸念される外国からの輸入豚に頼らず「国産の安全性の高い銘柄豚を育てたい」という強い意思のもと、他県へ赴いたり、大学などの研究機関と協力しながら、納得がいく銘柄豚を創出する研究を重ねました。そして試行錯誤のもと、肉質を決める餌を、天然由来のネッカリッチ(木酢酸)と、パン粉主体のエコフィード、笹サイレージを配合した飼料に決め、美味しく安全で高品質な豚肉を生産することに成功します。広葉樹の木炭と木酢液を配合した「ネッカリッチ」は、豚肉特有の獣臭を消すことができます。宮崎大学と県の畜産試験場と一緒に開発した「エコフィード」は食パン工場で不要になった耳の部分等を利用したもので、肉質にサシが入り柔らかくなります。そして放置竹林を活用した「笹サイレージ」は竹笹を粉砕して作られる次世代飼料肥料のホープ。乳酸菌効果で腸内環境を良くし、肉質と脂質が格段に高まります。

大切に育てた豚肉をあますことなく有効活用
最適な調達体制を整え、ようやく誕生したブランド豚「観音池ポーク」。丁寧に自然の力で育てた自慢の肉は、豚特有の臭みがなく、キメ細やかな柔らかさととろけるような食感。直接お客様に届けたい、と2001年に直売店を設置しますが、豚1頭を丸ごと販売していく中では、ロース肉、バラ肉のように常に需要がある部位と、どうしても残ってしまうモモやウデ等の需要の少ない部位が出てきました。こだわって育てた豚のどの部位にも、絶対に有益な価値を見出したい、破棄する事や、廉価販売はしたくないと模索し、新たに惣菜部門を立ち上げます。そして女性部が試行錯誤を重ね、「豚の全てを味わって欲しい!」と、観音池ポークをあますことなく活用したメンチカツ・コロッケ等を誕生させました。

都城の新たな官民連携施策「都城メンチ」誕生
現在売上の主要となっている観音池ポークのメンチカツ。売上急増のキッカケはとあるケーブルテレビの飛び込み取材でした。「美味しい!」という声が数回放送されるうちに、どんどん人気に火がついていきました。遠く離れた人達にも届けたいという想いから、専門家から冷凍技術を学び、細胞破壊が起きない急速冷凍で一年の消費期限ができるように。これによって販路が格段に拡大し、売上が比例していきます。そんな中、お肉王国だからこそ作れる、豚だけじゃない新鮮な牛肉や鶏肉を使った商品があることや、店舗ごとに特徴があるメンチカツのポテンシャルを見込んだ、博多大丸の九州探検隊との連携により、大丸の持つバイイング力と都城市の資源を有効に活用した官民連携による、都城市の地域産品を推した“ 都城メンチプロジェクト”が誕生します。
未来へのビジョン構築を明確に、一人一人が意識する
観音池ポークは2012年に六次産業化・地産地消法に基づく「総合化事業計画」認定を受け、ハードのバックアップもあり順調に売上を伸ばし、従業員数も増えていきました。しかし元々養豚農家の家族経営だったので、会社経営に移行する組織作りの難しさに壁が立ちはだかります。打開策として、6次産業化エグゼクティブプランナーによる人材育成研修を導入。講義に訪れたのは、農林水産省農山漁村事業において実績のある経営コンサルタントの庄司和弘さん。早速社員に招集がかかり、人材育成支援が開始されました。一番に挙げられた課題は「観音池ポークの未来を考える」。これに向け、一社員それぞれが描く、会社としてのビジョンを出してまとめていくこととなりました。繰り返していくうちに少しづつ意識がまとまり、将来に向けたビジョンが統一され明確になり、役割を意識できるように。そして各部門にリーダーを設置し、リーダーとしての意識付けを施しルールを作っていくと、バラバラだった方向性が統一されていくように。就業規則、規律、経営理念も庄司さんと社員、生産現場のスタッフともコミュニケーションをとりながら繰り返し、練り直していきました。

利益を確保するための仕組みづくり
現場では庄司さんのアドバイスにより、利益を確保するためにはどのように行動するか、という意識付けが行われました。まずは実際時間を測って一つ一つの商品原価計算を全てやり直し。減価償却を計算して成形する機械を導入、作業効率をあげる事に注視。それにより赤字決算がなくなりました。原価計算は現在も定期的に見直しをしているそうですが、「現場主義」が一番大事。そのために環境整備を整えることは必至、ということを学ぶことができました。
地域の人に愛されるものづくり、信頼されるブランド確立
現在馬場さんは事業継承のため、幹部がやるべき仕事の洗い出しをしています。ランク毎にtodoを色分けし、優先順位を付けています。何よりも大事なことは、これからも地域に愛される企業であること、そして地域を盛り上げていくため、地域との共存をより丁寧にすること。そして次への新しいステップのために、更にブランド力と認知を高めていき、自信を持って、地域の人に未来永劫愛されるものづくりをする会社を目指しています。