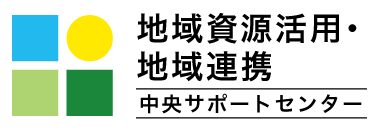私が貢献できること
私の専門性は、対話と協働を軸に、多様な関係者を巻き込みながら地域資源を活用した事業を創出することです。岩手県大槌町では、官民連携のジビエプロジェクトや、町の湧水と酒米を活かした日本酒開発を主導しました。これらの経験を通じて、ゼロから事業を立ち上げる際の合意形成プロセスと、持続可能な仕組みづくりを実践。経営コンサルティング、商品開発、販売拡大等のスキルを駆使し、単なる開発に終わらない、地域に根付く事業の実現に貢献します。
■ 得意分野の実務経験・支援実績の概要・成果
| 年月日 | 地域 | 農林水産物 | 専門分野 | 概要・成果 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/05-2022/03 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | ジビエ(鹿肉) | 関係人口創出 | 関係人口創出 ~地域課題をソーシャルビジネス化し、3年間で2.2万人の関係人口を創出したプロジェクト~ 【概要:複合的課題とプロジェクトの背景】 私が立ち上げに参画した岩手県大槌町は、東日本大震災津波により県内最大の人口減少率を記録し、交流人口も震災前の水準に回復しないという深刻な課題を抱えていました。さらに、年間1,000万円以上に及ぶニホンジカの農林業被害と、その対策を担うハンターの高齢化・担い手不足は、地域の基幹産業と生活環境を脅かす喫緊の課題となっていました。 一方で、駆除された鹿は活用されずに廃棄され、地域に根付く伝統的な食肉処理技術も、商品化や販路開拓のノウハウ不足により宝の持ち腐れとなっていました。 このような「人口減少」「鳥獣被害」「6次産業化の壁」という、一見すると別々の複合的な課題を統合的に解決するため、私は国の地方創生推進交付金を活用した「大槌ジビエソーシャルプロジェクト」を構想し、その立ち上げと推進に中心的な役割で関わりました。本プロジェクトの核心は、有害鳥獣であるニホンジカを「地域を繋ぐハブとなる資源」と再定義し、社会的課題の解決プロセスそのものを、地域内外の人々を惹きつけ、継続的な関わりを生み出す「関係人口創出事業」へと転換することにありました。 【アプローチ:事業の設計と私の役割】 私はプロジェクト全体のコーディネーターとして、持続可能な事業モデルの設計と、多様な関係者を巻き込む実行体制の構築を担当しました。 持続可能な『ジビエサイクル』の構築 単発の事業で終わらせないため、「捕獲」→「加工」→「販売」という従来のサプライチェーンに、「学び・体験(ジビエ塾・ツアー)」→「担い手育成」という要素を加え、人とお金が地域内で循環する『ジビエサイクル』という独自のソーシャルビジネスモデルを設計しました。これにより、食肉・製品販売による経済的な自立性と、人材育成による社会的な持続性の両立を目指しました。 多層的な関係人口を創出するプラットフォームの設計 関係人口を最大化するため、オンラインとオフラインを組み合わせた多角的なアプローチを取りました。全国の潜在顧客と繋がる「ECモール」と、熱量の高いファンを育てる「オンラインサロン」を構築。同時に、ジビエツアーやPRイベント等のリアルな体験機会を提供することで、商品の購入者からイベント参加者、そして将来の移住者や事業の担い手まで、多様な深度の関わりしろを意図的にデザインしました。 官民協働による推進体制の構築 行政(大槌町)、猟友会、民間事業者、農協、大学など、立場も目的も異なる関係者の間に立ち、それぞれの強みやリソースを活かせる官民協働の推進体制を構築しました。私がハブとなって定期的な連絡調整会議を運営し、プロジェクト全体の進捗管理と有機的な連携を促進しました。 【成果】 これらの取り組みの結果、本プロジェクトは計画期間である3年間(2020~2022年度)で、当初の目標を達成する顕著な成果を上げることができました。 定量的成果: 最大の目標であった**「ジビエに係る関係人口及び交流人口」は、3年間で累計22,440人を創出**しました。これは、オンラインプラットフォーム利用者(累計14,550人)、PR事業による交流人口(累計7,800人)、ジビエサイクル事業に係る関係人口(累計90人)を合算した数値であり、事業開始前の「0人」から飛躍的な増加を実現しました。 定性的成果: 持続可能な事業基盤の確立: 官民が連携し、地域課題を持続可能なソーシャルビジネスとして推進するプラットフォームが構築され、交付金事業終了後も自走できる体制が整いました。 地域資源の価値創造: これまで「害獣」として扱われていたニホンジカが、町の新たなブランドアイコンとなり、経済的・社会的な価値を生み出す「地域資源」へと転換されました。 先導的モデルの構築: 本プロジェクトで構築したオンラインプラットフォームは、同様の課題を抱える近隣市町村や他地域も参画可能な設計となっており、広域連携に資する先導的なモデルとしての価値も有しています。 |
| 2024/07- | 岩手県一関市大東町京津畑地区 | ウドや山菜 | 農山漁村資源活用 | 岩手県一関市大東町京津畑地区の農事組合法人「京津畑やまあい工房」は、ウドや山菜の栽培・加工、弁当・総菜の製造販売を中心に、廃校を活用した「京津畑交流館 山がっこ」での食事提供や宿泊対応も行っている。組合員15名(常勤5名)の平均年齢は75歳と高齢化が進み、地域の生活インフラを担いつつも、労働力不足、原価意識の低さ、販売先の限界といった経営課題を抱えていた。販路は地元産直、高島屋カタログギフト、年2回の「まごころ便」などで構成されるが、価格設定は物価高騰に十分対応しておらず、利益確保が難しい状況であった。 私は地域プランナーとして、まず経営改善の基盤づくりに着手した。具体的には、主力商品の「日替わり弁当」と「清庵弁当」の原価計算を実施し、材料費・包材費・光熱費・人件費を明確化。その結果、日替わり弁当は1個あたり109円の赤字、清庵弁当は364円の黒字と判明した。これを踏まえ、利益率1割以上を確保する価格設定の必要性を共有し、サービス品の有料化や容器変更によるコスト削減を提案。容器は見栄えを保ちつつ内容量を抑えられるタイプに変更し、仕入れ業者の見直しも行ったことで、提供コストの削減と高齢者にも食べやすい分量調整を両立できた。 販路拡大策としては、2025年4月開業の「道の駅だいとう」活用計画を立案。弁当・総菜・菓子類の販売は決定しており、地元食材をアピールするシールやインスタグラムへの誘導カード制作を提案。また、来訪型の販売促進として、「山がっこ」を拠点に木工体験や京津畑神楽の体験公演など、地域資源を活かした集客イベントを企画した。特に神楽公演は自治会主導で2027年7月開催を目標に準備が進んでいる。 ギフト販売「まごころ便」については、内容量調整による価格改定を実施。発注件数は減少したが、売上は前年並みを確保。加工委託品「食べる甘酒」のオリジナル品を新設し、ギフトの魅力向上にも取り組んだ。 経営戦略面では、現状の主力メンバーの高齢化を踏まえ、5〜10年後を見据えた人材戦略の必要性を提示。地域おこし協力隊の募集や弁当配達要員の確保を中期計画に組み込み、業務分担やデジタル化による事務効率化も提案した。また、情報発信力強化としてSNS(インスタ、Google)活用の学習・実践計画を策定し、フォロワー数の具体的な目標値を設定した。 これらの取組により、原価意識と価格設定の見直しが進み、販路拡大と集客施策の方向性が明確化された。今後は、2025年度売上目標1,850万円、2027年度2,150万円を達成し、利益を地域雇用に還元する体制づくりを進める。支援の成果として、組合員が自ら数字を把握し、利益確保を前提とした商品設計・販売戦略を検討できる土台が整ったことが大きい。今後も短期的な売上拡大と、中長期的な担い手育成の両輪で支援を継続していく予定である。 |
| 2021/07-2024/03 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | 酒米、湧水 | 農山漁村資源活用 | 関係人口創出 ~開発プロセスを「共創の場」とし、地域の新たな誇りを醸成した日本酒ブランド化プロジェクト~ 【概要:地域の宝を紡ぐ、新たな価値創造への挑戦】 岩手県大槌町の町内飲食店を活用した交流人口増加と地域食材のブランド発信事業の一環として、私は「湧水を活用した日本酒のブランド化」プロジェクトに、事業全体のコーディネーターとして参画しました。 本プロジェクトの目的は、単に新しい特産品を開発することではありませんでした。大槌町が誇る地域資源、すなわち酒米研究会の農家が丹精込めて育てる酒米「吟ぎんが」と、希少な動植物が生息する清らかな「源水の湧水」、そして南部杜氏が受け継ぐ醸造技術。これら地域の「宝」を掛け合わせ、その製造プロセスに多くの人々を巻き込むことで、商品への愛着を超えた「地域の新たな誇り」を醸成し、持続的な関係人口・交流人口を創出することにありました。 【アプローチ:多様な主体を繋ぎ、価値を最大化するコーディネート】 私はプロジェクト全体の「ハブ」となり、構想から商品完成、そしてファン獲得までを一貫してコーディネートしました。 「地域共創」を核とした座組みの設計 企画の初期段階から、この日本酒を「地域おこし酒」と明確に位置づけ、多様な関係者が「当事者」として関われる座組みを設計しました。生産者(大槌酒米研究会)、醸造家(株式会社浜千鳥)、行政(大槌町役場)はもちろん、水源を守る漁協、プロモーションを担う観光協会、販売を担う町内事業者、そして未来を担う地元の小中学生(ラベルデザイン協力)まで、総勢7つ以上の主体を繋ぎ、それぞれの想いやリソースを結集させ、プロジェクトを推進しました。 開発プロセスそのものを「体験コンテンツ」へ転換 消費者を単なる「お客様」ではなく「ファン」として巻き込むため、開発プロセスそのものを参加・体験できるコンテンツとして企画・実行しました。春の「田植え体験会」、秋の「稲刈り体験会」、冬の「仕込み体験会」には、それぞれ町内外から約50名が参加。さらに、商品名やラベルデザインを町民参加のワークショップで決定し、その様子を動画で発信するなど、プロセスを徹底的に「見える化」することで、発売前から商品への期待感と愛着を育みました。私自身も、酒造りの心臓部である仕込み水の運搬(合計4.2トン以上)に杜氏や漁協職員と共に携わるなど、現場に深く入り込みました。 ストーリーを伝える多角的なPRと持続可能な仕組みづくり 完成までの物語を伝えるため、特設WebサイトやPR動画の制作、新聞・テレビ・WEBメディアへの戦略的な情報発信、各種イベントでの試飲会などを包括的に企画・実施しました。さらに、売上の一部(720ml瓶1本につき20円)が水源の環境保全活動に寄付される仕組みを構築。商品を購入する行為が、地域の美しい自然を守る活動に繋がるという付加価値を創造し、ブランドへの共感を高めました。 【成果】 これらのコーディネート業務を通じて、本プロジェクトは目覚ましい成果を上げることができました。 定量的成果: 地域おこし酒「源水 純米吟醸」は、2022年11月のお披露目会で当日販売分が完売するほどの盛況ぶりを見せ、その後も順調に販売を伸ばし、ふるさと納税の返礼品としても好評を博しました。 田植え、稲刈り、仕込み体験といった一連の体験プログラムには、延べ100名以上の町内外からの参加者を集め、リアルな交流の機会を創出しました。 地元の小中学生を対象としたプレミアムラベルのデザイン募集には約80名の応募があり、地域の子どもたちが自分たちの町の資源に関心を持つきっかけを作りました。 定性的成果: 「オール大槌」での価値共創モデルの確立: 多様な立場の人々が、それぞれの役割を果たしながら一つの目標に向かって協働する「プラットフォーム」を創出し、町の新たな成功事例となりました。 新たな観光資源としての価値創造: モニターツアー参加者からは「大槌に来たら買うようにしたい」「他の日本酒と差別化できるコンテンツ」といった声が寄せられ、日本酒「源水」とその背景にあるストーリーが、大槌町の新たな観光資源としての価値を持つことが証明されました。 シビックプライド(市民の誇り)の醸成: 商品開発のプロセスに多くの町民が関わったことで、自分たちの町の資源や技術に対する誇りと愛着が育まれました。 |